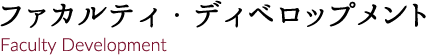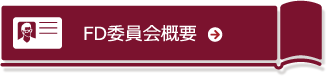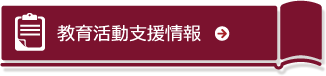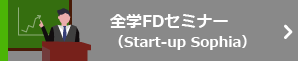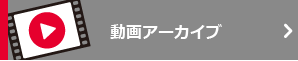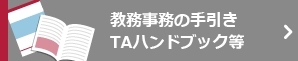ニュース 各部門の活動 2024年度
上智の基盤教育と文学部
- 主 催:
- 文学部・文学研究科
- 講 師:
- 開会の辞:寺田 俊郎 教授(文学部哲学科、文学部長)
報告者 :大塚 寿郎 教授(文学部英文学科、元基盤教育センター長)
柴野 京子 教授(文学部新聞学科、前基盤教育センター長)
武田なほみ 教授(神学部神学科、現基盤教育センター長)
閉会の辞:長尾 直茂 教授(文学部国文学科、文学研究科委員長)
司会 :中川 亜希 教授(文学部史学科、文学選出 FD委員会委員) - 日 時:
- 2025年1月15日(水)17:00~18:30
- 実施方法:
- 対面(学内)
- 参加者数:
- 47名
概要
趣旨
本学の基盤教育センターが発足したのが2021年7月、2022年度に新しい基盤教育が始まり本年度で三年目、来年度完成年度を迎えることとなる。以前の全学共通教育に引き続き現在の基盤教育にも、文学部は多くの科目を提供している。
そこで、上智の基盤教育の構想、設立、運営に携わって来られた方々のお話を伺い、自由闊達な意見交換を行って、ともに考え、基盤教育の意義を再確認し、文学部と基盤教育の連携についてあらためて考えることを本年度の教員FDの主題とした。
研修内容
本研修では、上智の基盤教育の原点と現在を知る先生方からお話を伺い、基盤教育の意義や文学部との連携について考えた。まず、報告者から以下の情報が共有された。
・基盤教育の原点について
原点は、専門分野に限らず学びの基盤を作ることであった。上智大学はワンキャンパスで学科間の垣根が低く、横のつながりがある点が強みであるため、それを全学共通科目まで広げてはどうかと考えた。自分の興味を探し、将来学ぶための基礎を身につけてもらうという構想があった。
全学生が入学前に「学びを学ぶ」という科目を履修し、上智のルーツ、教育精神、カリキュラムの構成、留学などについて学ぶ。全学共通科目のコア科目に新しく加わったのがクリティカルシンキングと表現力を身につけるための「思考と表現」、データを読む基礎的な力を身につける「データサイエンス」である。
課題となったのは学科科目との融合をどのようにするかという点であり、連携の方法、卒業単位への組み入れ、全学共通科目と学科科目の関係の見直しなどを検討する必要があった。
・必修授業「思考と表現」について
2022年に新カリキュラムが始動し「思考と表現」が必修となった。課題文を読んで著者やその問いについてディスカッションをしながら考えるという内容である。意見文とレポートを提出し、互いにピアレビューをしながら、文章の書き方や、学問体系と複数の思考パターンなどについて学ぶ。
図書館の使い方についても指導した結果、授業を履修した学生による図書館の貸し出し数が増加した。また、レポート作成のためソフィア・アーカイブズ関連資料を利用する学生もいた。ライティング・ラボについては高学年の利用も増えてきている。
来年度で2022年入学生が4年生になるため、卒論などに成果が反映されるかどうかを注視したい。
・上智大学の基盤教育について
基盤教育は主体的な学びの力の基盤を築くことが目的であり、学びを自分のために使うのではなく、学びで世界をつなぎ、和解をもたらし、希望のエージェントになってもらいたい。
ライティング・ラボ、データサイエンス・クリニックに加え、「思考と表現」の授業で図書館を扱うと図書館の利用率が上がるなど、自立的学習支援ができていると感じるが、特定の学生が繰り返し利用していたり、学生の関心が漠然としていたりすることから、本当の意味で学習支援ができているか疑問もある。高学年向け科目に演習科目を配置するなど、さらなる充実に向けた検討も必要である。また、教員不足や共通シラバスに則った運営による教員の負担の問題など、必修科目の安定的な運営に向けた課題もある。
続く質疑応答、意見交換の時間では、教養教育の在り方やそれが目指す方向性について、またデータサイエンスの学びを人文学においてどのように活用すべきかについてなど、意見交換が行われた。